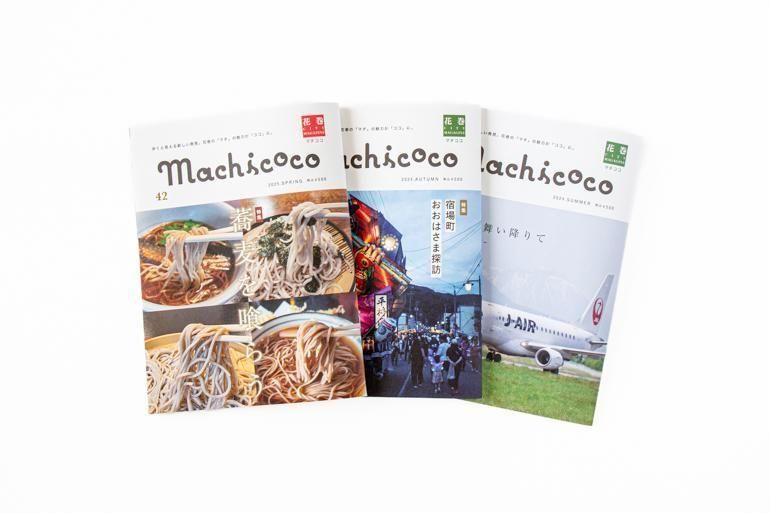IWATE STAR BRAND ロングインタビュー:畠山了一工場長「“お隣様”に愛される味を守り続けて」
創業100年以上の歴史を誇る佐々長の工場長を務める畠山了一さん。
佐々長の隣家で生まれ、佐々長の傍で育ってきた畠山さんは、2007年から工場長として全商品の味の責任を負ってきた。
全国的な知名度が高まってきている中で、昔ながらの "佐々長の味" を守るために、どのような想いで作り続けているのかを伺った。

畠山了一(hatakeyama,ryouichi)
1957年生まれ。土沢小学校、東和中学校、東和高校、東京農業大学卒業。
大学で醸造を学び、卒業後に佐々長醸造株式会社に入社。入社以来製造に従事し、2007年に工場長に着任。

畠山さんと佐々長
長かった東北の冬が終わり、春の陽気が満ちてきた5月。その温い外気を一瞬で忘れさせるようなひんやりとした空気が、蔵の中には漂っている。
「小さい頃は、この蔵でよく遊んだもんだよ」
冷気と諸味(もろみ)の香りが充満する蔵の中で、畠山さんは大きな木桶を眺めながら話してくれた。
岩手県のほぼ県央に位置する花巻市。
宮沢賢治が生誕し、多くの温泉があることで知られる花巻市の市街地から車で20分。のどかな田園風景を通り過ぎ、ユニークな町の活性化で知られる土沢の穏やかな町並みに入ったところに、佐々長醸造はある。
畠山さんは、佐々長の工場の隣家で生まれた。
お父様も佐々長で醤油関係の杜氏(現在の工場長の立場)を務め、幼いころから佐々長の傍で育ち、時には手伝いをしてきた畠山さんにとって、佐々長は本当に身近な存在だった。
高校卒業後、「自然な成り行き」で、味噌・醤油の醸造を勉強するために東京農業大学へ進学する。在学中、佐々長が東京近郊の物産展に出店する際には、アルバイトとして手伝いをしたのだという。
当時の副社長から、卒業後には地元に戻り佐々長に入るように打診され、自然な流れで佐々長へ入社することになる。
畠山さんの人生は、常に佐々長と共にあった。

佐々長に浸みこんでいる、二代目社長の言葉
「味で評判になるような商品を作れ」
幼いころから佐々長の傍で育った畠山さんの頭には、佐々長の二代目社長、佐々木連太郎氏が何度も何度も繰り返すこの言葉が、働く以前から浸みこんでいたのだという。
畠山さんは入社してから現在に至るまでずっと製造に携わってきた。その間、先の言葉を佐々長の信条として常に貫いてきたのだという。
"工場長は、何か独自の信条を持って取り組んできたのか" と問う私に、畠山さんはこう答えてくれた。
「佐々長に伝わる想いをしっかり守り続けること、それだけを常に大事に考えてきたんです。だから自分のコンセプトはないんですよ(笑)。それを守り続けることが、評判に繋がり、商売としても発展していく。そうずっと信じてきたんです。何よりもお客様に気に入ってもらい、喜んでもらえるように、おいしさだけを追求してきました」
お客様に喜んでもらうために、という佐々長の昔からの想いは、長きに渡り佐々長醸造全体に浸透し続けてきたのだ。

伝統の佐々長の味を作る、昔ながらの作り方、人の手、職人の技
佐々長の製品は、昔ながらの手法を守って作り続けている。(勿論部分部分に作業機械は導入している。)
例えば生醤油は、80年以上使われている秋田杉の大きな木桶で1年もの間熟成させている。
その大きな木桶が蔵に整然と並んでいる姿は壮観だ。
製造の自動化・金属タンクでの発酵、という大手メーカーの製造現場をイメージしていた私はその製造現場を覗いた時にそのイメージとの大きな違いに驚いた。

定期的に成分の分析検査はするものの、大豆に水分を吸わせる時間、蒸す時間、麹を作る時間、諸味の発酵時間、天地返しをするタイミング、加熱の温度等々…佐々長では細部から全体に渡るまで、全ての判断が作り手に委ねられ、工場長が最終判断を下している。
"佐々長の味" としていつも変わらない味が求められる以上、私の素人考えでは、なぜ、"作業に「ぶれ」が発生すると考えられる昔ながらの手法" にこだわる必要があるのか分からず、思わずその疑問を口にした。
「岩手には岩手の味がある。全国的な味を作る必要はないんですよ」
そう畠山さんは笑い、その隣で営業推進部部長の菅原さんが丁寧に説明してくれた。
「大手メーカーのように大量の原料を輸入して大量に作れば、味はある程度均質化できるかもしれません。でも、例えば佐々長の生醤油では全て岩手の原材料を使用していますが、年によって原材料自体の味が大きく異なるんです。その他にも作る季節や、気温等、常に異なる環境の中では、いつも同じ作り方をすると同じ味にはできないんですよ。
いつも"佐々長の味"として同じ味に保つためには、どうしても人の手を介する必要があるんです。成分が同じでも、同じ味にならないくらいですからね」

「佐々長の生醤油は口に入った時にあとから出てくる、引きずるようなうまみが強い。佐々長の生醤油はうまみを味わってほしいと思っています」
と畠山さんは佐々長の醤油の特徴を教えてくれた。
しかし、常にも異なる環境の中で、佐々長の生醤油の特徴であるうまみを安定して引き出すのは、至難の技だという。
「原材料の質は吟味しているのですが、必ず味には違いがあるので、手に入れた原材料にどれだけのタンパク質が含まれているか毎回把握しています。そのタンパク質の量によって熱をどれだけ加えるべきか、どれだけの発酵時間を必要とするのかいうことは感覚的に持っている。それは1年、2年でできるようになることではなく、長い経験と感覚が必要なんです」
原料の大豆は、年や種類によってタンパク質の多寡のみだけでなく、どれくらい水分を吸うか、蒸し上がるか、糖分や窒素・うまみがどれくらい出るかも全く異なるのだという。
しかも、佐々長の味に重要なうまみを出すことはどこか一つの工程だけでできるものではなく、大豆を仕込む最初の瞬間から、最後まで全ての工程で丁寧に工夫を重ねることで、やっと独特のうまみが生まれるのだという。

つゆ(老舗の味 つゆ)にも、独特の難しさがある。
カツオ節から秘伝の独特の手法で煮出したダシがつゆには使われているが、
原料となるカツオ節は、届くたびに全く味が異なるのだという。
カツオ節の状態で味見をし、どうダシを取るか、どのくらい時間をかけるか、数種のカツオ節をどう組み合わせるか等を全て職人の経験、感覚で判断し、いつも変わらない "佐々長の味" を作り上げているのだという。(つゆでは味だけでなく色も、いつも同じ "佐々長の色" にする必要がある。)
「レシピがあっても、それだけでは絶対に同じ味は作れない」という畠山さんの言葉には納得だ。
佐々長が昔ながらの作り方を続けるのにも理由がある。
佐々長の生醤油は、80年以上のものも存在する秋田杉の大きな木桶で1年間もゆっくりと自然に任せて熟成させている。
「木は水分量を調節してくれるんですよ。そして、佐々長のおいしい味を作り出せる酵母菌が木に入り込んでいるので、長らく愛されてきた佐々長の味になりますし、発酵も早くなるんですよ」
全て、昔ながらの本物の味、佐々長の味を出すための合理的な裏付けがあるのだ。
最後に、畠山さんはこんなことも教えてくれた。
「実は、季節によって味を多少変えているんですよ。しょっぱいものを好む季節、好まない季節、といったように人の感覚は季節によって微妙に変化する。勿論、変化させるのは規格の範囲内でですが、 "夏味と冬味" というように僅かに味を変えているんです」
どんな原料でも、どんな気候の年でも、お客様に喜んでもらえる "佐々長の味" にするには、
人の手、職人の技が必要なのだ。

佐々長の未来を想う
「日経新聞 何でもランキング」の専門家が選ぶつゆで「老舗の味 つゆ」が1位に選ばれ、
百貨店でも取り扱われるようになるなど、認知度が全国的に広まってきている佐々長。
畠山さんはそのような現状を受けて、これから佐々長がどうなっていくことを望んでいるのかを聞いてみた。
「全国レベルになることはありがたいけど、でも、一番の基本は地元で愛され続けることだと思っています。地元や岩手県で愛されない味が、全国レベルで愛されるはずがないですからね。
私はずっと、隣近所がおいしいと言ってくれて、喜んでくれることを一番に考えて作ってきました。隣近所や地元で、愛され続けるものを一生懸命作る。
そうして作った商品だからこそ、東京でも愛してもらえることがあるのだと思っています」
"全国で有名になる" といったような気持ちではなく、それとは正反対とも言える "身近な人" を喜ばせたいという思いが、結果として全国に佐々長のファンを広めているのだと、畠山さんの笑顔を見ながらそう感じた。

いつまでも、"お隣様" に愛される味を
畠山さんをはじめ佐々長で働いている人達は皆、地元で愛されてこそ、という想いがあるのだという。
「岩手の原材料で岩手の味を作り、身近な人がおいしいと喜んでくれることが一番うれしいんです。やはり、二代目の社長に幼い頃から言われ続けてきたことが、洗脳ともいえるくらいに頭の中にこびりついているんですよね」
その想いはずっとぶれることなく、何十年もおいしい味を熟成させ続けて来た木桶のように、大切に引き継がれているのだ。
最後に、畠山さんは、ご自身が心からの佐々長のファン、という表情で、畠山さん勧めの食べ方を教えてくれた。
「佐々長の生醤油は、うまみが自慢できると思っています。野菜にかけたい。特におひたしにかけるのが好きですね。
つゆ(「老舗の味 つゆ」)は、だしの取り方が独特で、こだわっているので、醤油とダシの醸し出す絶妙な味を味わってほしい。つゆは、やっぱり夏のそうめんに使うのが最高に好きだね」
妥協しないぶれない想いと、手間ひまを惜しまない工程、積み重ねた豊かな経験と研ぎ澄まされた感覚が、いつも変わらず地元で愛され続ける佐々長の味を作り出している。
ひんやり冷たい空気が充満する蔵にどっしりと並ぶ何十年も大切に使われ続ける木桶の中で、佐々長の味が静かに熟成していく鼓動を感じながら、日々畠山さんは佐々長の想いを愚直に守り続けている。
お隣様に愛されること。岩手で愛されること。
その想いを胸に、一心に身近な人達に愛されるものを作り続けることが、全国にたくさんの"お隣様"が生まれることに繋がると信じて。
>>佐々長醸造はこちらから